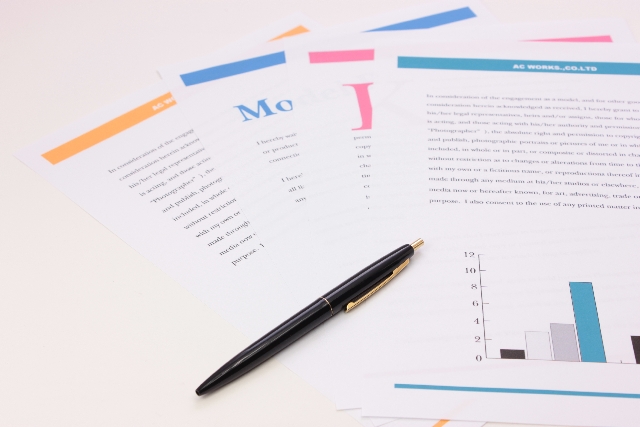


パートタイマー(事務職)を障害者枠で受ける場合について
当方、大阪市内に住む33歳で発達(精神)障害者で男性です。
この度、ハローワークの紹介で、企業3社に応募することになりました。
パートタイムの面接を受けること自体初めてですし、障害者枠で受けることも初めてなんですが、
●志望動機
●自己PR(長所・短所)
●障害の特性上、配慮してほしいこと
●会社への質問
を言えるようにしておけば大丈夫でしょうか?また、面接は障害者枠でパートタイマーの場合、何分くらいなんでしょうか?ご教示願えたら幸いです。
ちなみに私は今まで一般枠で、総合病院総務(1年・正社員)~某都道府県学校事務職(6年・正規公務員)~私立大学事務職員会計課(1年・嘱託)をしておりました。
当方、大阪市内に住む33歳で発達(精神)障害者で男性です。
この度、ハローワークの紹介で、企業3社に応募することになりました。
パートタイムの面接を受けること自体初めてですし、障害者枠で受けることも初めてなんですが、
●志望動機
●自己PR(長所・短所)
●障害の特性上、配慮してほしいこと
●会社への質問
を言えるようにしておけば大丈夫でしょうか?また、面接は障害者枠でパートタイマーの場合、何分くらいなんでしょうか?ご教示願えたら幸いです。
ちなみに私は今まで一般枠で、総合病院総務(1年・正社員)~某都道府県学校事務職(6年・正規公務員)~私立大学事務職員会計課(1年・嘱託)をしておりました。
パートでも正社員でも面接の内容は変わりません。
障害に対して希望する配慮が増えるくらいです。
面接時間は会社によります。5分~15分といったところでしょう。
あまり緊張なさらずに頑張って下さい。
障害に対して希望する配慮が増えるくらいです。
面接時間は会社によります。5分~15分といったところでしょう。
あまり緊張なさらずに頑張って下さい。
将来は映画の『制作担当』になりたいのですが、具体的にどのような進路選択をすればよいのかがわかりません。
やはり映画制作についての専門学校に行くべきなのでしょうか?
はじめまして、閲覧ありがとうございます。
以前にも質問させていただきましたが核心に迫る回答を得ることができなかったので、再び投稿させていただきました。
私はこの度高校三年に進級したのですが、未だ卒業後の進路決定ができずに焦っています。
以前から心理学を学びたいと思い国公立大学への進学を志望していましたが、
最近になって将来は映画の『制作担当』になりたいと考えるようになりました。
そして最終的には、現場での経験を生かせるような映画監督になりたいと思っています。
しかし、その『制作担当』についての情報をなかなか得られずに困っています。
【13歳のハローワーク 公式サイト】によりますと、制作担当は
『プロデューサーの助手的な仕事をする。
プリプロダクション(撮影前の準備期間)では、おもにロケーション場所を探し、
監督や技術パートと相談して、撮影する場所を決めるという仕事をする。
撮影に入ると、撮影現場にいて、ロケーション場所の安全を確保したり、
食事の手配をしたり、各スタッフの調整にあたる。
プロデューサーは、撮影が実際に始まると、撮影現場から離れ、
予算や撮影スケジュールの管理、ポストプロダクション(編集や音入れなどの仕上げ)の準備、
宣伝配給の打ち合わせなどのデスクワークをする。
したがって、現場で制作の責任者となるのは、制作担当である。
制作担当は、まずプロデューサーの助手となって、体験を積み、プロデューサーから信頼を得なければならない。
制作担当のカリキュラムのある専門学校もあるが、学校を出て、すぐに制作担当になれるわけではない。』
…とあります。
現時点では映画については全くの素人なのですが、映画制作について本格的に学ぶならば、
やはり記されている通り専門学校に行った方がよいのでしょうか?
ちなみに私が志望しているのは、洋画ではなく邦画の制作担当です。
長くなってしまい申し訳ありません。
具体的な進路等、ご教示願います。
やはり映画制作についての専門学校に行くべきなのでしょうか?
はじめまして、閲覧ありがとうございます。
以前にも質問させていただきましたが核心に迫る回答を得ることができなかったので、再び投稿させていただきました。
私はこの度高校三年に進級したのですが、未だ卒業後の進路決定ができずに焦っています。
以前から心理学を学びたいと思い国公立大学への進学を志望していましたが、
最近になって将来は映画の『制作担当』になりたいと考えるようになりました。
そして最終的には、現場での経験を生かせるような映画監督になりたいと思っています。
しかし、その『制作担当』についての情報をなかなか得られずに困っています。
【13歳のハローワーク 公式サイト】によりますと、制作担当は
『プロデューサーの助手的な仕事をする。
プリプロダクション(撮影前の準備期間)では、おもにロケーション場所を探し、
監督や技術パートと相談して、撮影する場所を決めるという仕事をする。
撮影に入ると、撮影現場にいて、ロケーション場所の安全を確保したり、
食事の手配をしたり、各スタッフの調整にあたる。
プロデューサーは、撮影が実際に始まると、撮影現場から離れ、
予算や撮影スケジュールの管理、ポストプロダクション(編集や音入れなどの仕上げ)の準備、
宣伝配給の打ち合わせなどのデスクワークをする。
したがって、現場で制作の責任者となるのは、制作担当である。
制作担当は、まずプロデューサーの助手となって、体験を積み、プロデューサーから信頼を得なければならない。
制作担当のカリキュラムのある専門学校もあるが、学校を出て、すぐに制作担当になれるわけではない。』
…とあります。
現時点では映画については全くの素人なのですが、映画制作について本格的に学ぶならば、
やはり記されている通り専門学校に行った方がよいのでしょうか?
ちなみに私が志望しているのは、洋画ではなく邦画の制作担当です。
長くなってしまい申し訳ありません。
具体的な進路等、ご教示願います。
まず、映画の根本的な仕組みから知らなければなりません。
映画の撮影現場というのは、完全分業制で行われており、『制作担当』という仕事は、
雑用やロケ地の手配、弁当の手配や役者の世話などを行う『制作進行』という部署の上司です。
総称して『制作部』と呼びます。
制作部 『制作進行』→『制作担当』→『制作主任』→『ラインプロデューサー』→『プロデューサー』
という序列があります。
もし、映画監督になりたいのであれば、『演出部』という部署を目指すことになります。
昔は、
演出部 『サード助監督』→『セカンド助監督』→『チーフ助監督』→『監督』
という序列がありました。但し、監督というのは、職業ではなく、その時の役割なので、助監督をやりながら
たまたま、その映画だけ監督を頼まれるという様に、全ての映画で監督が出来る様になることを示すわけではありません。
ただ、最近は、助監督を経験していなくても、他の分野で認められれば、監督として頼まれることも多いので、一概には
助監督をやったほうがいいとは言えません。
ちなみに、制作部と演出部では、現場での役割もかなり違い、制作部から入って、映画監督というのは難しいでしょう。
映画監督は、主な仕事は、「役者に演技をつける」という仕事になります。
また、スクリプターや撮影部と話し合い、カット割りを考えたり、全体的な撮影方法を具体的に検討する仕事です。
監督が一番偉い訳ではなく、あくまで、監督も役割の中の一部です。
実際に撮影する撮影部などと、話しが出来なくてはならず、技術の事や、演技のことを考えなくてはいけないので、
精神的にタフで、知識も豊富であることが求められます。なので、助監督で勉強を積んで、そこで耐え抜いた人が
映画監督になることが多いです。
映画の世界に入る方法ですが、映画は、ほとんどフリーランスの人で構成されます。求人誌に募集はされていません。
なので、人脈が命です。ですから、撮影所が崩壊した現在では、専門学校の講師に認められ、映画の現場に誘われる
というのが、一般的な入り方です。
それか、かなり困難ですが、自主映画で賞を取って、映画の現場に誘われるようになるか・・・・。
専門学校に行くのが懸命でしょう。ただし、ほとんどの映画の専門学校がキビシイので、そこで挫折する人も多いです。
あなたの文章を読む限り、まだ、制作担当とプロデューサーと映画監督の違いがよく分からないようなので、
専門学校で基礎知識を学ぶことをオススメします。
専門学校なら、プロの現場の手伝いとかにも呼ばれますし。
それと、テレビとCMと映画は、それぞれ業界が違いますし、映像の認識も違います。
テレビの世界に入ったら、映画の世界に戻るのは困難です。映画をやりたければ、テレビの世界には行かないようにオススメします。
こんな私も、大学卒業後、映画の専門学校に入った学生ですが、学校自体、相当厳しいですよ。
兎に角、落ち込むことばかりですが、続けることが大切だと映画人には言われます。
やめたらそこまで、続けていればいつか、成功する日が来る。そんな世界です。
【参考】
(制作進行)
雑用全般、機材の運搬、ロケ弁当の手配、役者のお世話、本番中の通行人のストップ、ロケ地で問題が発生したときに
ロケ地の管理人に謝りにいく、スタッフの健康管理。現場を離れることも多いです。本番中の現場を見られないことも多いです。
(制作担当・制作主任)
制作進行の上司、指示をしたり、あとは、お金の管理など
(ラインプロデューサー)
現場付きプロデューサー。プロデューサーは現場にほとんどいないので、現場でプロデューサーの代行的な仕事をしたり、
お金の工面をする
(助監督)
サードは、カチンコ打ちと小道具管理、セカンドは衣裳管理と現場を統率し、指揮する。チーフは撮影スケジュール管理
助監督のセカンドが一番面白いとよく言われます。なぜならば、現場を回しているのは、助監督セカンドだから。
ちなみに、テレビのADと違い、助監督は演出の方面なので、特別な事がない限り、弁当を買いにいったりとかの現場から
離れるような雑用はしません。あくまで現場で活躍する職業です。
※アメリカと日本は映画の仕組みは違います。ここでは、すべて日本のパターンです。
映画の撮影現場というのは、完全分業制で行われており、『制作担当』という仕事は、
雑用やロケ地の手配、弁当の手配や役者の世話などを行う『制作進行』という部署の上司です。
総称して『制作部』と呼びます。
制作部 『制作進行』→『制作担当』→『制作主任』→『ラインプロデューサー』→『プロデューサー』
という序列があります。
もし、映画監督になりたいのであれば、『演出部』という部署を目指すことになります。
昔は、
演出部 『サード助監督』→『セカンド助監督』→『チーフ助監督』→『監督』
という序列がありました。但し、監督というのは、職業ではなく、その時の役割なので、助監督をやりながら
たまたま、その映画だけ監督を頼まれるという様に、全ての映画で監督が出来る様になることを示すわけではありません。
ただ、最近は、助監督を経験していなくても、他の分野で認められれば、監督として頼まれることも多いので、一概には
助監督をやったほうがいいとは言えません。
ちなみに、制作部と演出部では、現場での役割もかなり違い、制作部から入って、映画監督というのは難しいでしょう。
映画監督は、主な仕事は、「役者に演技をつける」という仕事になります。
また、スクリプターや撮影部と話し合い、カット割りを考えたり、全体的な撮影方法を具体的に検討する仕事です。
監督が一番偉い訳ではなく、あくまで、監督も役割の中の一部です。
実際に撮影する撮影部などと、話しが出来なくてはならず、技術の事や、演技のことを考えなくてはいけないので、
精神的にタフで、知識も豊富であることが求められます。なので、助監督で勉強を積んで、そこで耐え抜いた人が
映画監督になることが多いです。
映画の世界に入る方法ですが、映画は、ほとんどフリーランスの人で構成されます。求人誌に募集はされていません。
なので、人脈が命です。ですから、撮影所が崩壊した現在では、専門学校の講師に認められ、映画の現場に誘われる
というのが、一般的な入り方です。
それか、かなり困難ですが、自主映画で賞を取って、映画の現場に誘われるようになるか・・・・。
専門学校に行くのが懸命でしょう。ただし、ほとんどの映画の専門学校がキビシイので、そこで挫折する人も多いです。
あなたの文章を読む限り、まだ、制作担当とプロデューサーと映画監督の違いがよく分からないようなので、
専門学校で基礎知識を学ぶことをオススメします。
専門学校なら、プロの現場の手伝いとかにも呼ばれますし。
それと、テレビとCMと映画は、それぞれ業界が違いますし、映像の認識も違います。
テレビの世界に入ったら、映画の世界に戻るのは困難です。映画をやりたければ、テレビの世界には行かないようにオススメします。
こんな私も、大学卒業後、映画の専門学校に入った学生ですが、学校自体、相当厳しいですよ。
兎に角、落ち込むことばかりですが、続けることが大切だと映画人には言われます。
やめたらそこまで、続けていればいつか、成功する日が来る。そんな世界です。
【参考】
(制作進行)
雑用全般、機材の運搬、ロケ弁当の手配、役者のお世話、本番中の通行人のストップ、ロケ地で問題が発生したときに
ロケ地の管理人に謝りにいく、スタッフの健康管理。現場を離れることも多いです。本番中の現場を見られないことも多いです。
(制作担当・制作主任)
制作進行の上司、指示をしたり、あとは、お金の管理など
(ラインプロデューサー)
現場付きプロデューサー。プロデューサーは現場にほとんどいないので、現場でプロデューサーの代行的な仕事をしたり、
お金の工面をする
(助監督)
サードは、カチンコ打ちと小道具管理、セカンドは衣裳管理と現場を統率し、指揮する。チーフは撮影スケジュール管理
助監督のセカンドが一番面白いとよく言われます。なぜならば、現場を回しているのは、助監督セカンドだから。
ちなみに、テレビのADと違い、助監督は演出の方面なので、特別な事がない限り、弁当を買いにいったりとかの現場から
離れるような雑用はしません。あくまで現場で活躍する職業です。
※アメリカと日本は映画の仕組みは違います。ここでは、すべて日本のパターンです。
何故みんなハローワークに行くのですか??
townwork.、froma、マイナビなどから
自分で応募できるのに・・・
townwork.、froma、マイナビなどから
自分で応募できるのに・・・
ハローワークにしか掲載されていない情報もありますし
あと何人応募しているなど教えてもらえます。
何かトラブルがあったときにハローワークに相談することもできるからじゃないでしょうか。
ハローワークに掲載されている情報もハローワークを通さず直接応募することもできるんですよ。
でも決まった際にはハローワークにその旨連絡しなければいけません。
あと何人応募しているなど教えてもらえます。
何かトラブルがあったときにハローワークに相談することもできるからじゃないでしょうか。
ハローワークに掲載されている情報もハローワークを通さず直接応募することもできるんですよ。
でも決まった際にはハローワークにその旨連絡しなければいけません。
関連する情報